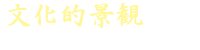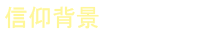
關渡宮創設に関しては、時代ごとに諸説あるため、ここでは簡単に幾つか紹介します。一つ目は關渡宮公式の見解で、魏姓の石興和尚が福建湄洲祖廟の媽祖と共に台湾に渡来した際、關渡の近くで豪雨に遭い、基隆河・淡水河が氾濫して足止めに遭ったと言われています。石興和尚が謹んで媽祖にお伺いを立てたところ、關渡に残る意向を示したため、この地に廟が建てられたと伝えられています。二つ目の説は、台湾宗教研究の日本の先駆者である増田福太郎氏によるもので、今から約200年前に、湄洲の船員が大媽を載せて台湾北部に渡航し、關渡に寄港した際、暗礁に乗り上げて船体が破損し、神像を大きな石の上に移しておいたところ、そのまま動かせなくなったと言われています。媽祖にお伺いを立てるとこの地に残る意向を示し、現地の林姓の者と協議した末に、廟を創設したとしています。廟の創設に関しては諸説ありますが、そのほとんどが海上信仰に由来するもので、多くの伝説が混ざり合っています。
關渡宮媽祖の神像は、大媽と二媽が最も霊験あらたかと言われ、様々な伝説が残されています。關渡宮の公式見解では、大媽は關渡宮の住職であった石興和尚が、湄洲祖廟の天后宮から台湾へ迎えた媽祖であるとしています。二媽に関しては、神像を乗せた船が海難事故に遭い、唭哩岸に流れ着いた神像を現地の農民が発見したことから、当初は慈生宮(主神は五穀先帝)に祀られていました。その後、廟の改装工事の際に關渡宮へ移したところ、完工してからも媽祖は「海の出入口」を見守り、海上を航行する船舶や漁民の安全を關渡宮で守護する意向を示したため、關渡宮二媽として残されています。このことから、旧暦1月16日には慈生宮から「獅陣」(獅子舞の決まった形態)や「鑼鼓」(銅鑼や太鼓)の行列が關渡宮へと出向き、盛大に二媽を慈生宮へと迎え、先帝公と共に唭哩岸一帯を巡ることから、「二媽回娘家」(二媽、実家に帰る)と言われています。また、学界ではこのような風習を日本統治時代の疫病を鎮める信仰と結び付け、二媽に祈願して人々の病害や虫害を払ったとされています。
媽祖にまつわる事跡はこれらに止まらず、日本軍による台湾占領初期の光緒21年(西暦1895年)に、大稻埕一帯で強盗事件が発生し、關渡の村落では一軒一軒つぶさに捜索が行われていましたが、關渡宮と周辺住民が反日行動に参加していたとの認識から、30軒余りの民家と媽祖廟が焼き討ちに遭います。媽祖像も灯油をかけて焼かれましたが、焼け跡からは顔面だけが黒くすすけた媽祖像が発見され、本体に損傷は無かったと伝えられています。その後、話を聞いた關渡対岸の蛇仔形の村民が、月明かりの夜に關渡に渡り、媽祖二体を救出して戻ると観音山麓の石壁脚に隠し、事件平定後に再び關渡宮に移設したと言われています。そのため毎年、黒面關渡媽祖と蛇仔形媽祖が巡行する行事が始まったとされています。
第二次世界大戦中は、淡水の飛行場に日本の横田部隊の水上飛行機が十数機配置され、關渡宮の前にある中港河傍のオオハマボウが生い茂る農地に隠されていました。このことを聞きつけた米軍は空爆を行いますが、米軍の飛行機が關渡上空で爆弾を投下すると、中国古代の女性が雲の端に現れ、スカートの裾で爆撃機の投下した爆弾を弾き、現在の關渡自然公園と大度路の近くに落としたと伝えられています。その後、媽祖像の外套に黒い焦げ跡が発見され、当時の住民は媽祖が外套を用いて爆弾を払い、人々の命を救ったと信じられています。
数百年に渡って人々と環境は変化し、漢民族が原住民族にとって代わって主要な民族となり、關渡の交通手段は水路から陸路へと移り変わってきました。關渡宮には霊験に関する多くの言い伝えが残されていますが、時を経ても人々にとって重要な拠り所であることは変わらず、民族・交通事情等の社会変化が生じたところで、關渡宮が人々の心の中に占める地位は揺るぎなく、それどころか時間と共により深く、強固に信仰が根付いてきたと言えます。